\今なら4大プレゼントを配布中!/
うまく開けない場合は、
🔗→右上「…」ブラウザで開く→アプリで開く
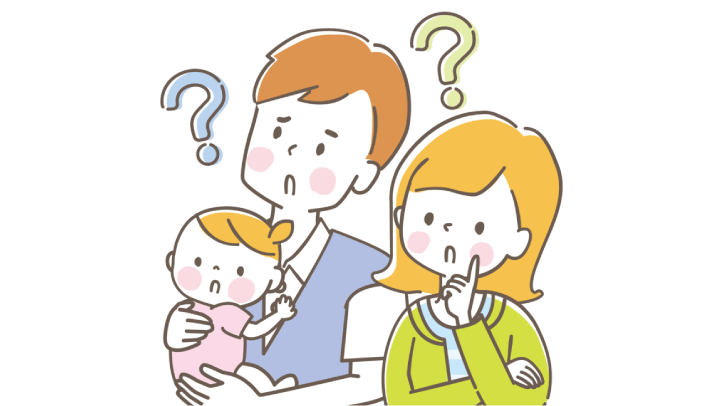

「服を着たがらない」「この音が嫌だ」――そんな子どもの言動に、戸惑ったことはありませんか?
実はそれ、単なるわがままではなく、背景に感覚過敏という特性が隠れていることがあります。
この記事では、あるお母さんから教わったエピソードをもとに、カウンセラーとして学んだ「感覚の違い」についてご紹介します。
感覚過敏とは何か、そして子どもたちが「イヤ」と感じる背景にはどのような事情があるのか、一緒に考えていきましょう。
そのお母さんは、小さい頃から校内放送の声が聞き取れなかったそうです。
この感覚は、大人になった今も続いています。ショッピングモールで流れる迷子放送も、「これ、みんな聞こえているのかな?」と不思議に思うのだそうです。
周囲の大人たちは「ちゃんと聞いて!」と言いますが、本人にとっては、意識してもどうにもならない違和感だったのです。
さらに興味深いのは、聞き取りたいと思っている店内アナウンスはうまく聞こえないのに、誰も気にしないような生活音――たとえば一階で稼働している乾燥機の音――は気になって眠れないことがあるということ。
「重要な情報は聞こえなくて、どうでもいい音はうるさいと感じる。まるで矛盾しているようだけど、これが私の“日常”だったんです」と語ってくれました。
また、私たちは「音が聞こえている=内容も理解できている」と思いがちですが、実際には「聞こえる」と「理解できる」は別物であることを、このお母さんは教えてくれました。
もし子どもが、放送や先生の話を「聞いていない」ように見えたとしても、それは怠慢ではないかもしれません。感覚のズレに苦しんでいるのかもしれないのです。

音楽を聴くときも、すべてが心地よく聞こえるわけではないといいます。
同じ「音」でも、受け取る人によってその快適さや不快感は大きく異なります。
このお母さんは、試行錯誤の末に自分にとって心地よい音の条件を見つけ出しました。
こうした音だと、不思議と落ち着くそうです。
私たちは、「普通の音だから大丈夫」と思い込んでしまいがちですが、普通が誰にとっても快適とは限らない。そう気づかせてくれるエピソードです。
子どもが音を嫌がるとき、それは単なる好き嫌いではなく、本当に耳が痛い、気持ち悪い、といった生理的な反応かもしれないのです。
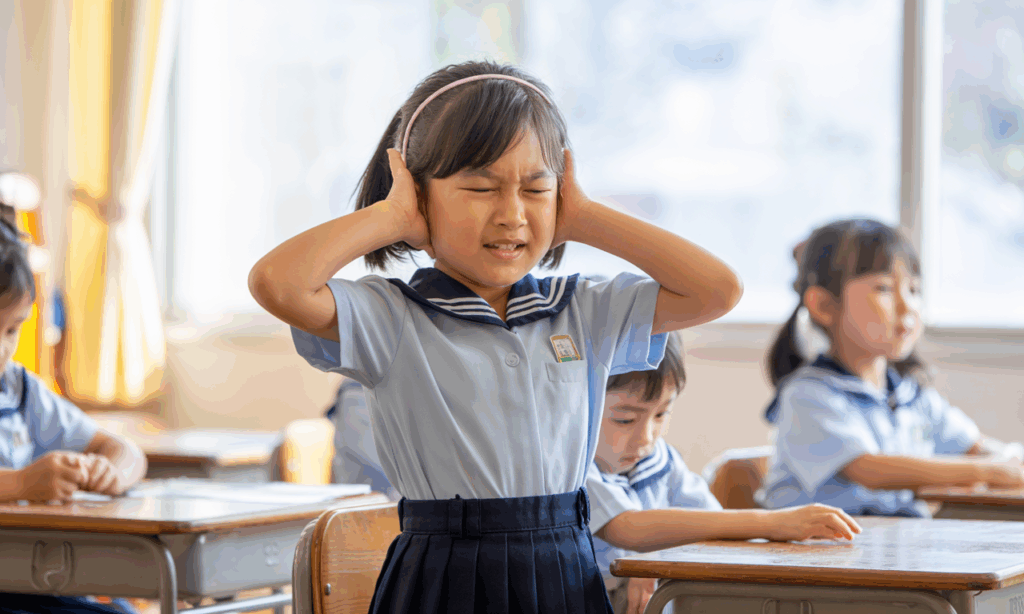
服に対しても、独自の感覚過敏があると話してくれました。
ただ、「タグを切っただけじゃダメなんです」とお母さんは言います。
大人の目からは「そこまでしなくても」と感じることでも、当事者にとってはそれが“身を守るための工夫”なのです。
新しい服を選ぶときも、試着して「大丈夫」と思っても、実際に長時間着てみると首元の締めつけや肩周りの違和感に気づき、着られなくなることがあるそうです。
一番快適に着られるのは、着古した旦那さんの綿のTシャツだそうです。
着古されて生地が柔らかくなり、身体に馴染んだTシャツ。新品では味わえない「無刺激」の安心感があるのだと言います。

こうした体験談からも、子どもが服を嫌がる理由が単なるわがままではないことがよくわかります。
こういったことに、本人も言葉ではうまく説明できないまま苦しんでいる場合があるのです。
私たち大人は、子どもが「イヤだ」と言ったとき、「わがままだ」と感じてしまうことがあります。
でも、感覚過敏を持つ子どもたちは、見た目にはわからない苦しみを抱えていることが多いのです。
大切なのは、子どもたちの「イヤ」の裏に、どんな感覚的な苦痛や不安が隠れているのかに目を向けることです。
たとえば――
こうしたサインを受け止め、「この子にとってどうすれば心地よく過ごせるだろう?」と考えることが、何よりのサポートになるのです。
このお母さんの話を聞いて、私は改めて思いました。
子どもたちの「こだわり」は、生きるための工夫なのだと。
環境に適応するために、自分にとっての最適な方法を必死に探している。けれど、その工夫はときに「わがまま」「甘え」と誤解されてしまうこともあります。
だからこそ、大人が「この子は何を感じているのだろう?」と想像することが大切なのです。

子どもの「イヤ」は、わがままではありません。
そのための大切なサインです。
どうか、お子さんの小さなサインに気づき、優しく寄り添ってあげてくださいね。
✨ もっと子どもの「生きづらさ」のサインに気づくヒントを知りたい方へ
当カウンセリングルームでは、カウンセリングを通して、 それぞれのお子さんに合わせた「心に寄り添うポイント」や「感覚過敏への対応のヒント」などを一緒に考え、サポートしています。
⬇️ ご相談・ご予約はこちらから
LINE登録:https://lin.ee/6rLs4RK
小さな気づきが、親子の毎日をもっと楽に、もっと優しく変えていきます。